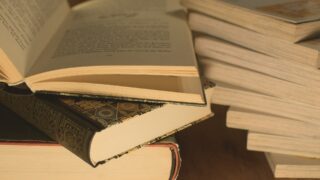いつかは誰にも起こり得る相続。
いつかは誰にも起こり得る相続。
受ける側のときもあれば最後は相続する側になります。
そんな相続ですが最近は相続時に揉める件数がふえてきて「争族」なんて言葉も耳にします。
そして相続の際には税金も発生します。このような事から「相続は難しそう」と思われている方が多いです。
今回はまず、相続時の負担を減らす為に最低限抑えておくべきポイントについて触れていきます。
この記事を読んでいただくと相続時の負担を減らす為に抑えておくべき最低限のポイントがわかり、ご家庭にて取り組むべき準備を判断する為の一助になるかと思います。
この記事の結論
結論としては、
相続時の負担を抑えるためのポイント(前準備)としては
・生命保険の活用(生命保険の非課税枠の利用をする。)
・生前贈与の活用(生前贈与を利用し相続財産を減らす。)
・財産の整理(不要な土地などは処分し現金化して分割しやすくしておく。)
等があります。
遺留分対策としても活用されることも多いかと思いますがまずはこの3つかと思います。
他にも色々な方法はありますが、この3つのことに取り組んでおくだけで相続時の負担が減るかと思います。
あと1つだけ最低限抑えておくべきポイントとして、
「相続税の基礎控除」があります。
税金を納める必要があるのか?いくら納めなくてはいけないのか?がわかり対策しやすくなるためです。
相続税の基礎控除とは?
相続税には基礎控除があります。
基礎控除額の計算式は、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
となります。
※例、法定相続人が2人の場合で、相続額が4000万円の場合。
例、3000万円+(600万円×2人)=4200万円
となります。
上記の場合だと、相続財産が4200万円以内の場合は、基礎控除にて非課税で受け取れることになります。
法定相続人とは?
法定相続人とは相続の権利がある人です。
ケースバイケースで変わりますが、
父、母、長男、長女
のような家族構成で、
父が亡くなった場合は、母、長男、長女が法定相続人になります。
父に兄弟や親がいた場合でも同じです。
遺産分割割合については、
(母・・・50%)、(長男・・・25%)、(長女・・・25%)となります。
仮に長男が亡くなっていた場合は長男の子が法定相続人になります。
生命保険の活用
生命保険の死亡保険金には非課税枠があります。
控除額の計算式としては、
500万円 × 法定相続人の数
法定相続人が3人の場合は、死亡保険金1500万円までは非課税で受け取れることになります。
※注意点としては、
上記の非課税枠が使えるのは
契約形態が、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で受取人が相続人の場合のみです。
保険金の非課税枠に入らない例として
・契約者と被保険者が違う
・入院中に亡くなった場合の医療保険の給付金は、生命保険の非課税枠にはならない。
などです。
ざっくりお伝えすると、
自分の体にかける保険を自分で払って受取人を相続人に設定してください。
遺族の生活の支えになるような契約形態の死亡保険金に非課税枠が使えます。
保険関係の税務はこちら→【お金の話】個人の生命保険の税務。貯蓄性保険や給付金には税金かかるのか?
生前贈与の活用
生前贈与を活用して、相続の対象となる財産を減らしておくことも準備となります。
例えば有名なのは毎年、約100万円位を贈与し贈与税非課税枠内(110万円)での贈与を行っていく方法がメジャーかと思います。
※上記の場合は、毎年何か利用目的があり、タイミングや金額が違う必要があります。
※相続時から遡り相続財産と判断される場合があります。
財産の整理
不要な土地や財産を処分しておくのも準備になります。
例えば住宅とその土地しか相続財産が無い場合は、誰か住み続ける場合は遺産の分割が困難になります。最悪の場合、遺産分割のために土地や建物を売却する例もあります。住む場合は保険等を活用し遺産分割の支払い対策も必要です。
土地や建物が複数ある場合に1箇所ずつ相続しても価値や維持費が違う場合が多くトラブルになる傾向があります。
不要な土地や分けづらいものは心苦しい部分もあるかと思いますが、先に処分しておいたり名義変更をしておくこも大切です。
まずは、必要か?不要か?を判断するところから取り組まれてはいかがでしょうか?
本記事のまとめ
本日のまとめとしては、最低限抑えてほしいポイントをご紹介しました。
ただでさえ悲しいことが起こっている相続の際に、心の負担だけでも計り知れないのに経済的な負担や時間的な負担を抑える為に、取り組みをご検討いただければと思います。
この記事が皆様の悩み解決の一助になれば幸いです。
お読みいただきありがとうございました。
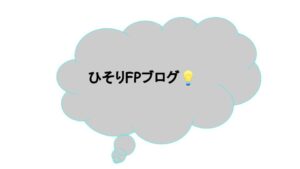 ひそりFPブログ 2022年12月開設
ひそりFPブログ 2022年12月開設
このブログでは、普段FP(ファイナンシャルプランナー)として活動していく中で、私自身が「もっと早くから知っておきたかったこと」、「絶対に知っておいたほうが良いこと」をメインに投稿していき、皆様の日々の生活や問題解決の一助になれればと思い、日々執筆しています。
私自身が、学歴もなく何も知らないまま損をしていたり失敗をしてしまった経験があります。
正直、後悔の念もあります。
そんな私も子どもが出来、子どもたちには自分のような後悔はしてほしくないと思うようになってきました。
そして、綺麗事ではなく、私が出会う方にも子どもさんがいたり、大切なご家族のために同じ想いをしてほしくないなと思っています。
情報があふれるこの時代でブログを書いたからと言って何名の方の目にとまるかも見ていただけるかもわかりません。
ですが、見ていただいた方のなにか一つでもお役に立ち、実生活に活かせれるような投稿ができればと思っています。