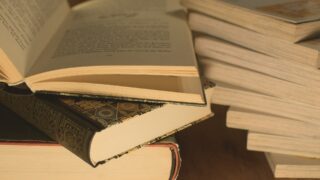子どもさんが産まれたら進められる事が多い学資保険ですが、果たして本当に必要なのでしょうか?
この記事を読んでいただくと、将来の子どもさんの為の資金作りのイメージを固める一助になるかと思います。
この記事の結論は?
では、学資保険に加入したほうが良いかどうかですが、
私の個人的な考えで結論を出すと
「学資保険には加入しない」
が結論になります。
理由としては
・超低金利だから
・他の方法が良いと思うから
です。
では、学資保険とその他の商品と比べてみたいと思います。
そもそも学資保険とは?
そもそも学資保険とはどのような商品なのか確認していきます。
学資保険とは、一般的な商品説明をすると
子どもさんが18歳になると満期金がでてきます。
例えば満期200万円で契約していると、子どもさんが18歳になると200万円もらえるというシンプルな内容です。
その出てきたお金を大学の入学金や授業料などに当てていくたの貯蓄のような性能です。
もちろん18歳で就職される場合は、就職の準備の費用に当てても使い方としては問題ないです。
保険性能については、契約者(親)に万一の事があった場合は、月々の保険料(掛け金)は不要になる(払わなくてよくなる)が子どもが18歳になると、約束の200万円はもらえるという内容です。
更に入院特約などがついているタイプもあります。
学資保険以外の選択肢?
私は上記でご案内した学資保険より別の方法が今の時代にあっていると思います。
(決して学資保険を否定しているわけでは有りません。)
ただ、現在の学資保険は返戻率(払った金額に対して、いくら戻ってくるかの比率)が
現在は元本割れのものが増えてきています。
保障がついているから仕方ないですが。
私個人的な意見を述べさせてもらいますと、
とはいえ、学資保険を検討されている方の目的は
「将来の教育資金を貯めること」です。
私の持論としては、貯蓄は貯蓄、保障は保障と割り切って分けたほうが良いと思っています。
貯め方としては、つみたてNISAや変額保険や外貨建保険があります。
私は現状(2023年1月現在)だと外貨建保険よりも、つみたてNISAや変額保険が良いと思っています。
外貨建保険や変額保険について今後記事を書こうと思っています。
つみたてNISAに関しては以前の つみたてNISAとは?
をご覧いただければと思います。
まとめ
まとめとしましては、私の個人的な考えだと現状としては
「学資保険には加入しない」そして、別の商品で資産形成をしていく。
というのが時代には合っているのかなと個人的に思っております。
正解は有りませんが、
ただ、上記を理解した上で保障として学資保険に入りたいという方もいらっしゃるかもしれません。
まずは将来いくら必要なのか?
そもそも、いくらかかるのだろうか?
をご家族で話し合ってから考えられてみてはいかがでしょうか?
お読みいただき、ありがとうございました。
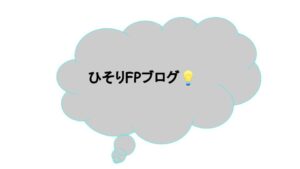
ひそりFPブログ 2022年12月開設
このブログでは、普段FP(ファイナンシャルプランナー)として活動していく中で、私自身が「もっと早くから知っておきたかったこと」、「絶対に知っておいたほうが良いこと」をメインに投稿していき、皆様の日々の生活や問題解決の一助になれればと思い、日々執筆しています。
私自身が、学歴もなく何も知らないまま損をしていたり失敗をしてしまった経験があります。
正直、後悔の念もあります。
そんな私も子どもが出来、子どもたちには自分のような後悔はしてほしくないと思うようになってきました。
そして、綺麗事ではなく、私が出会う方にも子どもさんがいたり、大切なご家族のために同じ想いをしてほしくないなと思っています。
情報があふれるこの時代でブログを書いたからと言って何名の方の目にとまるかも見ていただけるかもわかりません。
ですが、見ていただいた方のなにか一つでもお役に立ち、実生活に活かせれるような投稿ができればと思っています。